与沢翼の書籍 「ブチ抜く力」
|
|
前回の第4章「健康の法則」につづいて、「ブチ抜く力」の本日は第5章を解説します。
数えきれない豪快・キレキレなエピソードをもつ与沢翼さん。
会社解散前は「派手な金持ち」を演じていたと回想するとおり、女遊び・超高級車・数々のメディア露出など世間を騒がせたものでした。
一転して、現在の私生活では「愛する妻と子供を守る気持ちしかない」そうです、
ここ数年の劇的な人生体験を経て、家族で寄り添うあたたかさの様なものを感じたのでしょうか。
現在はドバイに居住。
もちろん十分稼いだからと言って家族サービスだけしている様な与沢氏ではありません。
積極的な不動産投資はいまも健在のようです。

一例でいうと、数億で購入した(もちろん現金一括払い!)東京赤坂のタワーマンションの一室。
貸し出すことが決まり、ただ「鍵を引き渡す」ためだけに日本に帰国。
超多忙ななかでも仲介業者を一切いれず、自分で借主に鍵を渡すそうです。
不動産業者を介さないとなると、広告手段としてはSNS。
部屋の借主は「Twitter」で一般募集。
なんと投稿から30秒で決まったとのこと!
ちなみに家賃は月々88万円だそうです。
自ら物件を探し、自ら鍵の引き渡しまでこなす与沢氏の情報収集、そして解析力。
それではその与沢氏の「情報収集の法則」をご紹介いたします。
「ブチ抜く力」全6章の内容
第1章(基本の法則)
すべての根底にある大原則
第2章(ビジネスの法則)
人と群れるな。誰とも組まず単独で突っ走れ!
第3章(投資の成功法則)
勝負は、チャンスが来る前から始まっている
第4章(健康の法則)
一日一日を全力で。その積み重ねが大きな結果に繋がる!
第5章(情報収集の法則)
情報収集も3週間。「一人突っ込み」を繰り返し、センターピンを掴まえろ!
第6章(未来予想の法則)
これからの世界で起きる事を予測し、逆算して今から動こう!
第5章(情報収集の法則)

情報収集・分析をする際は「3週間」を目安にする。
与沢氏はそのように勧めています。
この3週間でやるべきこと
- 情報収集と登場人物を押さえる
- 分析・検証
- 最後にセンターピンを見つける
これだけだと何をいっていて具体的に何をすればいいのかわかりませんよね。
しかし、これが一番効果のある方法だそうです。
順に説明していきます。
「3週間」徹底してやる!
なぜ3週間?とお思いでしょう。
これは与沢氏の感覚的なものだそうですが、だいたい一つのことを集中してやり抜くには「3週間」というのが長すぎず短すぎず、ちょうどいい期間なのだそうです。
また、情報は時がたつと古びていくので短期間で重点的にインプットするのがオススメと言います。
そして与沢氏の経験値として、一度なにかを3週間やり抜くと、その間に経験値が「爆発的に」、カイジ風にいうと「悪魔的だぁ〜〜〜」という風に効率化が進むのだそうです。
やり抜くことで自信にもつながり、当たり前のレベルが上がることでしょう。

わたしも何かの本で読んだなかで、「21日習慣」というワードを思い出しました。
人間は21日、つまり3週間で身につくか身につかないかがだいたい決まるそうです。
例えば「今日から毎日トイレ掃除しよう!」と思いたったとします。
はじめは自分で良いことだと思って決めたことなので勢いがあります。
しかしそのうち忘れ始めたり、面倒臭くなりはじめて「いまトイレ掃除より重要なことをやってるから」などとやらない言い訳を無意識に探しはじめ、数日で続かなくなる・・・
とういことも珍しくありません。
これが21日間(3週間)やり続けられたとき、人ははじめて「習慣化」されはじめるそうです。
ちなみに私がそうでした。
今ではトイレ掃除をしないと歯を磨いていないのと同じくらい「気持ちが悪い」状態になりました。
それをしないと「気持ちが悪い」レベルまでいけば、もう完全に習慣化といえます。
1週間ごとにリサーチレベルを3段階に分けていくという手法だそうです。
それでは3週間を1週間ずつに分けた各段階の行動を見ていきましょう。
- 1週目 「全体像を把握する」
- 2週目 「推論を立てる」
- 3週目 「センターピンを設定する」
1週目「全体像を把握する」

はじめの1週目は、情報収集しようとすることの全体像から取り掛かる。
全体を俯瞰する「鳥の目」とミクロの視点で物事を分析する「虫の目」という言葉があります。
最初に新しい知識を入れようとした場合、「鳥の目」を重要視して全体像やそのテーマに関わる一般法則やルールを知ること。
「つかみ」ですね。
与沢氏はまず最初の1週間目はその世界の「「勢力図」を頭に叩き込み、
「この世界で起きていること」
「その世界の登場人物」
「相関関係」
などの流れを把握しておくことで、「これから起こりうる事象」を予想しやすくしているようです。
ちなみに「登場人物」とは必ずしも人間とは限りません。
例えば仮想通貨にチャレンジするとします。
その世界の登場人物といえば
ビットコイン、イーサリアム、リップル、その他などなど。
その仮想通貨という世界で今起こっていることや、最低限おさえておくべきルールや仕組みなどをリサーチし、それぞれの力関係など相関関係を知ることから始めます。
2週目 「推論を立てる」

2週目は、集めたデータ基に「自分の推論」を立てていくそうです。
この週から「分析」が始まります。
まずは「登場人物」の強みと弱み、特徴を分析。
株式投資なら「なぜこの会社は強いのか」というテーマに対して、
「規模が大きいから」
「歴史が長いから」
「利益率が高いから」
など他社との差別化ポイントを探す作業をするようです。
さらに検討する項目として、
「もっと強くなるには?」
「足りない部分や弱みは?」
要は集めたデータを「掘り下げる」わけですね。
そして2週目の終盤には自分の解析した内容を踏まえて
「今後伸びそうな会社は?」
「来年トップをとる会社は?」
などと自分なりに予測をする訳です。
この2週目の作業がこれからの戦略に欠かせない「基盤」となるため、この2週目はものすごく重要といえます。
3週目「センターピンを設定する」

いよいよセンターピンの決断の時です。
センターピンとは以前の記事、「第1章 基本の法則」で触れたとおり
「ものごとの本質を掴まえる」こと
この2週間にわたって得た知識や推測をもとに、センターピンとして設定すべきことは何かを考える。
要は自分が選択・決断する基準となる「軸を決める」わけです。
例えば「車の購入」でいえば、何を基準にして選び、決断するか。
「このカラーは絶対譲れない」
「7人乗りが条件」
「遠出するからシートがフルフラットになる車種」
などなど、選択基準となる軸を決める。
ビジネスの世界で「なんとなく決めた」など他の人に論理的に説明できないようなレベルの意思決定では「ただの運まかせ」となってしまいます。
あなたが「独りで事業をしている」なら失敗しても自己責任ですが、お客様も同じ組織に属する仲間に対してこんな失礼なことはありません。
「なぜここにセンターピンを定めたのか」
その背景や経緯・裏付けなど、他の人にキチンと説明できるような決め方であれば、例え失敗したとしても次のチャンスももらえるでしょう。
「失敗したけど出来ることはやった」
何より自分が後悔しないでしょう。
同じ三振するにも根拠を持て

先日亡くなった「ノムさん」こと野村克也さんのエピソードです。
同じ三振でも2通りある。
「根拠のある」三振
「根拠のない」三振
ノムさんは監督時代、「根拠のある三振」には怒らなかったそうです。
「今日のピッチャーはいつもの直球の勢いがない。決め球に変化球を多投すると予想したからまっすぐに対応出来なかった」などと自分なりにピッチャーを観察して一打席に対する戦略をキチンと立てている。
三振した根拠を説明できます。
逆はどうでしょう?
ノムさんからしてみたら、
「何も考えずに、ただ来た球を打つ」
「バッターボックスに立つ準備もできてない」
そういうバッターにチャンスを与えたいでしょうか。
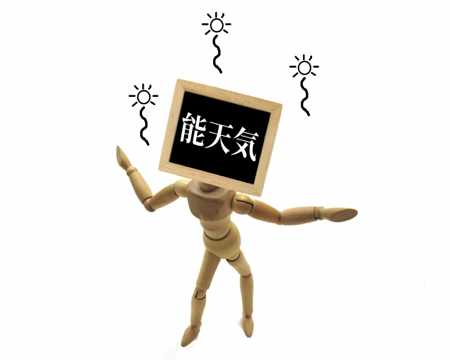
センターピンの話に戻すと、この判断基準をいかに正しいところに置けるようになるかは「訓練」が必要でしょう。
人生で何か新しい挑戦を始めるたびに、この3週間のリサーチ手法を用いて繰り返すことで、正しいセンターピンの掴み方、コツがわかってくると与沢氏は言います。
与沢氏の表現には独特ないいまわしもありますが、どれも物事を進めるうえで大切なことばかりです。
ビジネスだけでなく趣味や生活習慣にも使えますので、それぞれ挑戦する事柄に当てはめて実践してみましょう。
進歩するには素直に「モノマネ」することが大切です。
(次回はいよいよ最終章、第6章 ”未来予想の法則” です)
与沢翼の書籍 「ブチ抜く力」
ブチ抜く力【電子書籍】[ 与沢翼 ]
楽天で購入
[…]





